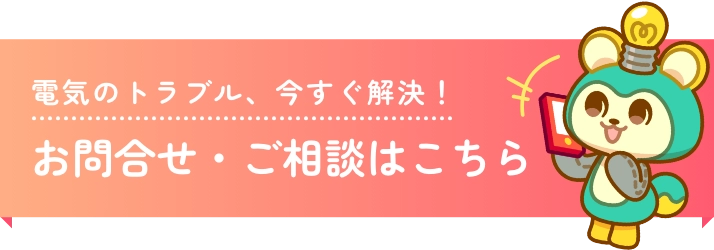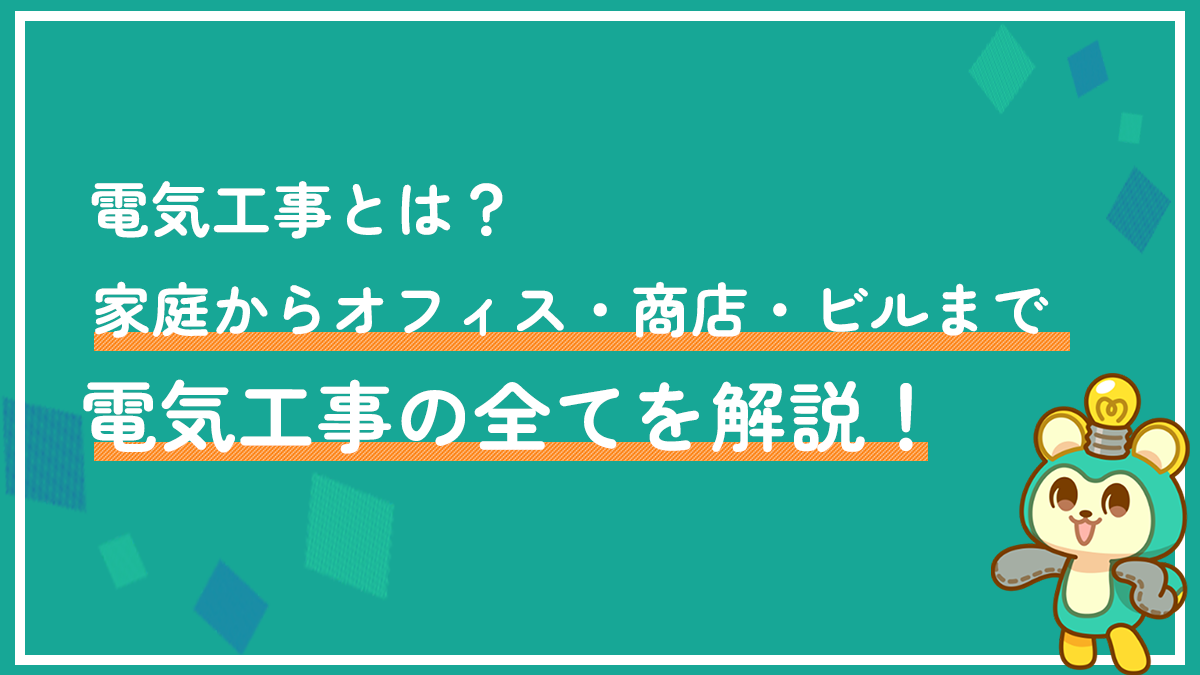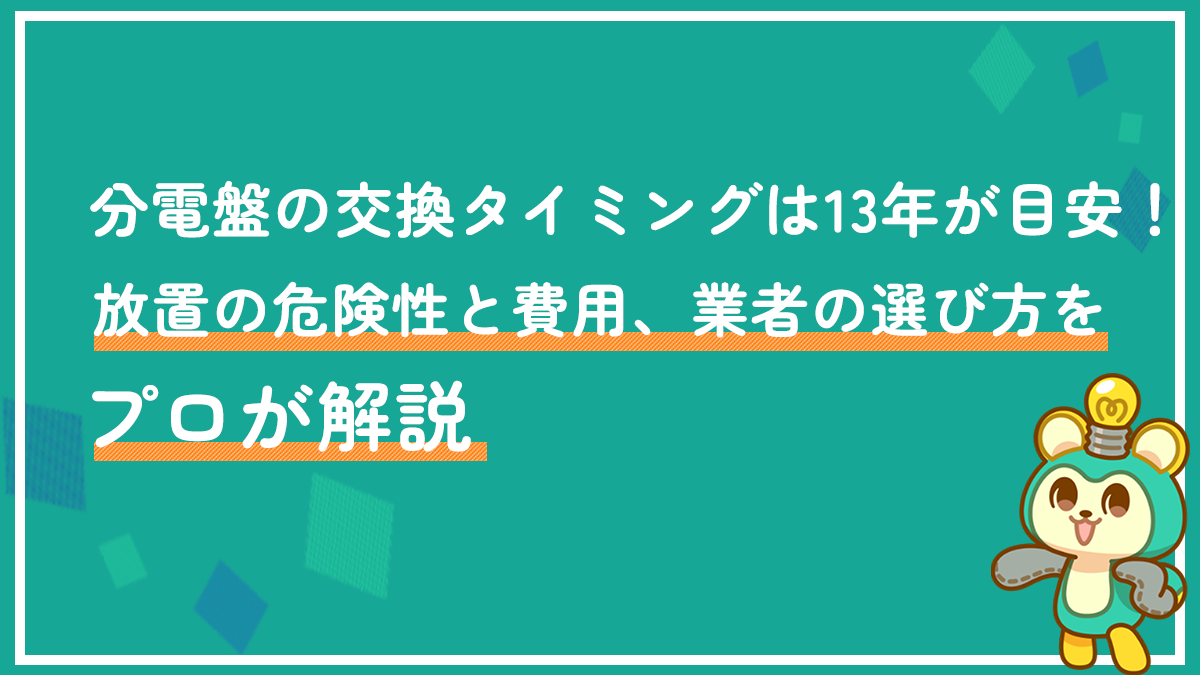分電盤のブレーカーが上がらない!原因と正しい対処法をプロが徹底解説
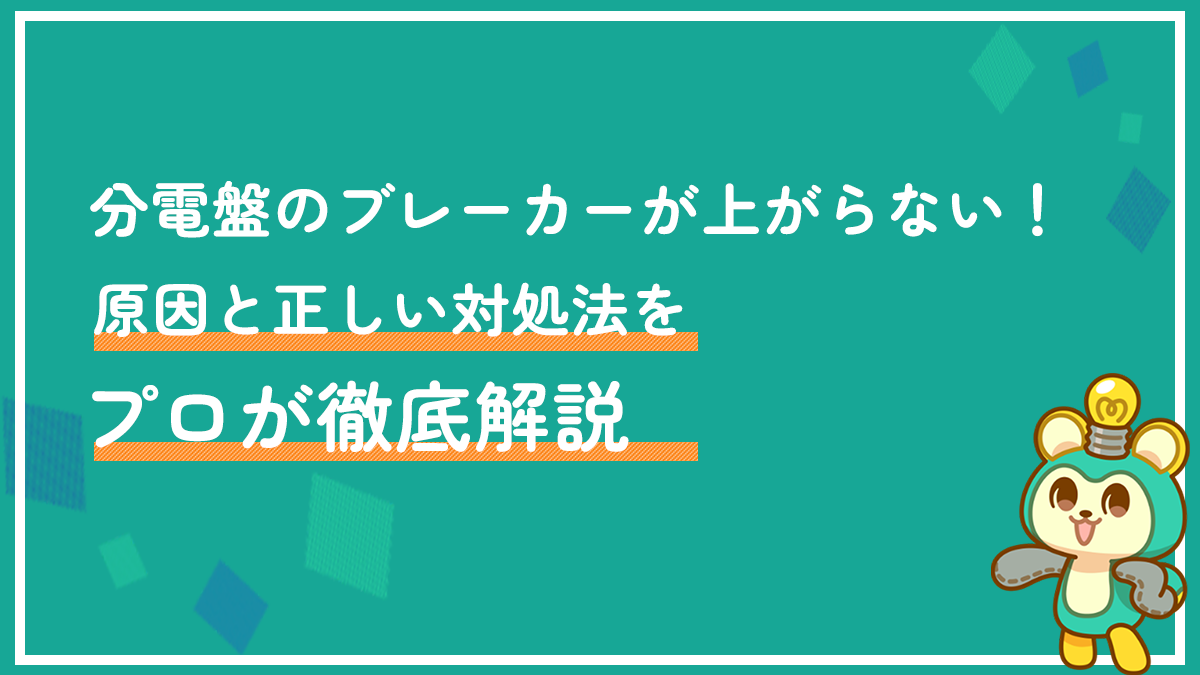
夜中に突然、家中の電気が消えて真っ暗に…。「またブレーカーが落ちたのか」と分電盤のレバーを上げようとしても、すぐに落ちてしまったり、そもそも上がらなかったりして、不安と焦りを感じていませんか?
「家電が壊れた?」「もしかして火事の原因に?」そんな心配が頭をよぎるのも無理はありません。
ご安心ください。この記事を最後まで読めば、電気に詳しくない方でも、ブレーカーが上がらない原因を落ち着いて見つけ、安全に対応できるようになります。
- どのブレーカーが原因かを見分ける方法
- 火災や感電を防ぐための、安全な復旧方法と注意すべきポイント
- 自分で対処すべきか、プロに依頼すべきかの明確な判断基準と費用相場
この記事は、数多くの電気トラブルを解決してきた国家資格を持つ電気工事士チーム「ピカくま」が、あなたの不安に寄り添いながら、プロの視点で徹底的に解説します。パニックにならず、まずはこの記事を読んで落ち着いて行動しましょう。
- ブレーカーが上がらないとき、まず確認したい3つのポイント
- 1. 周辺一帯が停電していないか?
- 2. 分電盤から異音・異臭はしないか?
- 3. どのブレーカーが落ちているか?
- 分電盤の基本|3種類のブレーカーの役割と見分け方
- アンペアブレーカー:家全体の電気契約を守る
- 漏電ブレーカー:感電や火災の危険を防ぐ
- 安全ブレーカー:各部屋・回路の異常を遮断
- 【種類別】ブレーカーが上がらない5大原因を徹底解剖
- 原因① 電気の使いすぎ(過負荷)
- 原因② 漏電
- 原因③ ショート(短絡)
- 原因④ ブレーカー本体の故障・寿命(約13~15年)
- 【写真で解説】ブレーカーを安全に復旧させる正しい手順
- どうしても上がらない…すぐに専門業者へ連絡すべき危険なサイン
- どこに連絡すればいい?ケース別の相談先一覧
- 賃貸物件の場合:まず管理会社・大家さんへ
- 持ち家の場合:信頼できる電気工事業者へ
- ブレーカーの修理・交換にかかる費用相場まとめ
- 関東・東海・関西なら最短即日!国家資格者が対応する「ピカくま」が安心
- もう落とさない!今日からできるブレーカートラブル予防策
- まとめ:ブレーカーが上がらない時は慌てず安全第一で対処しよう
ブレーカーが上がらないとき、まず確認したい3つのポイント
まずは焦らず、順番に確認しましょう。慌てて分電盤を触ると、感電や火災といった二次被害につながる恐れがあります。安全を確保しながら、状況を正しく把握することが解決への第一歩です。
1. 周辺一帯が停電していないか?
ご自宅だけの問題なのか、地域全体の問題なのかを切り分けることが重要です。
- 窓の外を確認する:近所の家やマンション、街灯の明かりはついていますか?もし周りも真っ暗なら、お住まいの地域一帯で停電が発生している可能性が高いです。
- 電力会社の情報を確認する:スマートフォンの電波が届けば、契約している電力会社(東京電力、関西電力など)の公式サイトにある停電情報ページを確認しましょう。復旧見込みなども確認できます。
周辺一帯が停電している場合は、ご自身でできることはありません。復旧を待つようにしましょう。もしご自宅だけが停電している場合は、分電盤に原因があると考えられます。
2. 分電盤から異音・異臭はしないか?
次に、分電盤に近づいて、音やにおい、熱などの異常がないかを確認します。
- 異音:「ジジジ…」「ブーン」といった普段は聞こえない音がしていませんか?
- 異臭:プラスチックが焦げたような、ツンとくる匂いはしませんか?
- 熱:分電盤のカバーやブレーカーのレバーが異常に熱くなっていませんか?
これらの症状が一つでも見られる場合は、非常に危険なサインです。漏電やショート、ブレーカーの故障が原因で、火災に発展する可能性があります。すぐに全ての操作を中止し、絶対にブレーカーには触らず、専門の電気工事業者に連絡してください。
3. どのブレーカーが落ちているか?
異音や異臭がないことを確認したら、分電盤のカバーを開けて、どのブレーカーのレバーが下がっている(「切」または「OFF」になっている)かを確認しましょう。これが、原因を特定するための最も重要な手がかりとなります。
レバーが「入」と「切」の中間で止まっている場合も、それは「落ちている」状態です。原因や対処法は、どのブレーカーが落ちているかによって大きく変わります。
分電盤の基本|3種類のブレーカーの役割と見分け方
「どこを触っていいかわからない」という不安を解消するために、まずは分電盤の主役である3種類のブレーカーについて理解しましょう。一般的な家庭用分電盤は、左から「アンペアブレーカー」「漏電ブレーカー」「安全ブレーカー」の順に並んでいます。
アンペアブレーカー:家全体の電気契約を守る
- 場所:分電盤の一番左側にある、最も大きなブレーカーです。
- 役割:電力会社との契約アンペア(例:30A、40A)を超えて電気を使いすぎた場合に作動し、家全体の電気を遮断します。
- 見分け方:「40A」などの数字が書かれており、電力会社によってはカラフルな色分けがされています。
- 補足:最近のスマートメーターが設置されている住宅では、このアンペアブレーカーがなく、遠隔で制御されるため分電盤に存在しない場合があります。
漏電ブレーカー:感電や火災の危険を防ぐ
- 場所:分電盤の中央に位置します。
- 役割:家の中のどこかで電気が漏れている(漏電している)ことを検知すると作動します。感電事故や漏電による火災を防ぐ、命を守るための非常に重要な安全装置です。
- 見分け方:「漏電ブレーカー」と記載があり、「テスト」と書かれた小さなボタンが付いているのが特徴です。
安全ブレーカー:各部屋・回路の異常を遮断
- 場所:分電盤の右側に複数並んでいる小さなブレーカーです。
- 役割:「キッチン」「リビング」「エアコン」など、各部屋や特定の家電製品の回路(コンセント)ごとに分かれています。その回路で電気を使いすぎたり、ショート(短絡)したりした場合に作動し、該当する回路の電気だけを遮断します。
- 見分け方:小さなスイッチがたくさん並んでおり、それぞれに部屋の名前などが書かれています。
【種類別】ブレーカーが上がらない5大原因を徹底解剖
ブレーカーが上がらない主な原因は、5つのパターンに分類できます。ご自宅の状況と照らし合わせて、どのブレーカーが落ちているかを確認しましょう。
原因① 電気の使いすぎ(過負荷)
最も一般的で、比較的安全な原因です。
- 症状:アンペアブレーカー、または特定の安全ブレーカーが落ちる。
- 具体例:エアコン、電子レンジ、ドライヤー、電気ケトル、食洗機など、消費電力の大きい家電を同時に使ったときに発生します。家全体で使いすぎればアンペアブレーカーが、特定の部屋で使いすぎればその部屋の安全ブレーカーが落ちます。
原因② 漏電
火災や感電につながる危険な原因です。
- 症状:漏電ブレーカーが落ちる。
- 具体例:家電製品の故障やコードの劣化、水回り(キッチン、洗面所、洗濯機など)での水濡れ、屋外のコンセントや配線の劣化などが原因で発生します。
原因③ ショート(短絡)
こちらも火災のリスクがある危険な原因です。
- 症状:安全ブレーカーが「バチッ!」という音と共に瞬時に落ちる。
- 具体例:コンセントに溜まったホコリと湿気が原因の「トラッキング現象」、傷んだコードの銅線同士が接触すること、プラグに金属片が触れることなどが原因で発生します。
原因④ ブレーカー本体の故障・寿命(約13~15年)
見落とされがちですが、ブレーカーも機械であるため寿命があります。
- 症状:特に電気を使いすぎていないのに頻繁に落ちる、レバーを上げてもすぐに落ちる、レバーが固くて上がらない、ブレーカー本体が熱い・変色している。
- 解説:ブレーカーの寿命は、一般的に13年~15年程度です。長期間使用していると内部の部品が劣化し、正常に働かなくなることがあります。このような場合は、ブレーカーの交換が必要です。
【写真で解説】ブレーカーを安全に復旧させる正しい手順
原因が漏電の疑いがある場合、正しい手順で復旧作業を行うことで、どの回路に問題があるのかを特定できます。必ず乾いた手で、足元が濡れていないことを確認してから作業してください。
【手順1】使用中の家電のプラグをすべて抜く
原因を特定しやすくするため、家中のコンセントから家電のプラグをすべて抜きましょう。照明もスイッチを切ってください。
【手順2】すべてのブレーカーを「切(OFF)」にする
分電盤のレバーをすべて下に下げます。
① 安全ブレーカー(右側の小さいもの)をすべて「切」にする。
② 漏電ブレーカー(中央)を「切」にする。
③ アンペアブレーカー(左側の大きいもの)を「切」にする。
※レバーが中間で止まっている場合は、一度完全に「切」まで下げてから操作します。
【手順3】主幹となるブレーカーを「入(ON)」にする
今度は逆の順番で、主幹となるブレーカーを上げていきます。
① アンペアブレーカーを「入」にする。
② 漏電ブレーカーを「入」にする。
※もしこの時点でどちらかのブレーカーがすぐに落ちる場合、分電盤自体が故障しているか、幹線部分で漏電が起きているなど、重大な問題の可能性があります。すぐに作業をやめて、専門の業者に連絡してください。
【手順4】安全ブレーカーを一つずつ「入(ON)」にしていく
アンペアブレーカーと漏電ブレーカーが上がった状態を維持できたら、いよいよ原因の回路を特定します。
① 安全ブレーカーのレバーを、一つずつ、ゆっくりと間隔をあけながら「入」にしていきます。
【手順5】落ちた回路が原因箇所!
安全ブレーカーを一つずつ上げていく途中で、再び漏電ブレーカーが落ちた場合、その直前に上げた安全ブレーカーの回路が漏電の原因です。
その問題の回路の安全ブレーカーは「切」のままにし、その回路に繋がっているコンセントや家電製品を詳しく調べてください。原因が特定できない場合は、その回路は使わずに専門業者に調査を依頼しましょう。他の問題ない回路の安全ブレーカーは「入」にすれば、家の一部で電気を使うことができます。
どうしても上がらない…すぐに専門業者へ連絡すべき危険なサイン
以下の症状が見られる場合は、ご自身で対処しようとせず、感電や火災のリスクを避けるために直ちに専門業者に連絡してください。
- 手順通りに復旧作業をしても、原因が特定できない、または復旧しない。
- 分電盤から焦げ臭い匂いや「ジージー」という異音がする。
- ブレーカーや分電盤の内部が焦げている、変形・変色している。
- 漏電ブレーカーのテストボタンを押してもブレーカーが落ちない(故障している証拠)。
- ブレーカーを操作する際に火花が出た。
- 少しでも作業に不安や危険を感じた。
あなたの安全が何よりも最優先です。無理な自己判断は絶対に避けてください。
どこに連絡すればいい?ケース別の相談先一覧
いざ専門家に頼るとなった場合、どこに連絡すれば良いのでしょうか。お住まいの状況によって連絡先が異なります。
賃貸物件の場合:まず管理会社・大家さんへ
アパートやマンションなどの賃貸物件にお住まいの場合、電気設備は大家さんの所有物です。必ず最初に管理会社や大家さんに連絡し、指示を仰いでください。
許可なくご自身で業者を手配してしまうと、修理費用が自己負担になる可能性があります。また、建物全体の電気設備に関わる問題の可能性もあるため、まずは管理者への連絡が鉄則です。
持ち家の場合:信頼できる電気工事業者へ
戸建てなどの持ち家にお住まいの場合は、ご自身で電気工事業者を探して依頼する必要があります。
分電盤の工事は、「第二種電気工事士」以上の国家資格を持つ人だけが行える専門作業です。資格のない人が工事をすることは法律で禁止されていて、とても危険です。料金だけでなく、資格や実績、アフターサービスの有無を確認して、信頼できる業者を選びましょう
ブレーカーの修理・交換にかかる費用相場まとめ
修理や交換を依頼する際に気になるのが費用です。あくまで一般的な目安ですが、事前に相場を知っておくと安心して相談できます。
| 作業内容 | 費用相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 点検・調査(絶縁測定など) | 5,000円~12,000円 | 基本的な出張費や点検作業の費用です。 |
| 漏電調査・修理 | 8,000円~20,000円 | 漏電している回路の特定と簡単な修理作業を含みます。 |
| ブレーカー交換(1個) | 15,000円~40,000円 | 部品代と作業費を含みます。ブレーカーの種類により変動します。 |
| 分電盤全体の交換 | 30,000円~70,000円 | 回路数や分電盤のグレードによります。工事時間は1~2時間程度です。 |
| 夜間・緊急対応料金 | +5,000円~10,000円 | 通常の作業費に加算される場合があります。 |
※注意: 上記はあくまで目安です。正確な料金は必ず作業前に業者から見積もりを取り、内容に納得した上で依頼するようにしましょう。
関東・東海・関西なら最短即日!国家資格者が対応する「ピカくま」が安心
「どこに頼めばいいかわからない」「今すぐ来てほしい」
そんな緊急事態でお困りなら、私たち「ピカくま」にお任せください。
- 国家資格者が必ず対応:第二種電気工事士の資格を持つプロが、安全第一で確実な作業をお約束します。
- 最短即日のスピード対応:関東・東海・関西の各エリアに密着。お電話一本で最短即日、あなたの元へ駆けつけます。
- 明朗会計・見積無料:作業前に必ず状況を確認し、詳細な見積もりをご提示します。不当な追加料金は一切いただきません。
実際にいただいたお客様の声です。
「夜遅くにもかかわらず、すぐに駆けつけてくれて助かりました。原因も丁寧に説明してくれて安心できました。」(40代・主婦)
「分電盤が古く、交換をお願いしました。作業がスムーズで、料金も見積もり通り。頼んでよかったです。」(50代・男性)
お電話、LINE、ウェブサイトのフォームから24時間365日ご相談を受け付けています。突然の電気トラブルは、我慢せず、まずはプロにご相談ください。
もう落とさない!今日からできるブレーカートラブル予防策
無事に電気が復旧したら、今後はブレーカーを落とさないための予防策を心がけましょう。
- 契約アンペア数を見直す:頻繁にアンペアブレーカーが落ちる場合、ご家庭の電気使用量に対して契約アンペア数が不足している可能性があります。電力会社に相談してみましょう。
- 消費電力の大きい家電を同時に使わない:電子レンジを使いながらドライヤーをかける、といった使い方を避けるだけで、過負荷によるトラブルは大幅に減らせます。
- タコ足配線をやめる:一つのコンセントにたくさんの機器をつなぐと、コードが熱くなり危険です。延長コードはできるだけ使わないようにしましょう。
- コンセント周りを定期的に掃除する:プラグとコンセントの間に溜まったホコリは、火災の原因(トラッキング現象)になります。乾いた布で定期的に掃除しましょう。
- 漏電ブレーカーのテストボタンを月一で押す:正常に作動するかを定期的にチェックする習慣をつけましょう。(テスト時は一時的に停電します)
まとめ:ブレーカーが上がらない時は慌てず安全第一で対処しよう
突然の停電でブレーカーが上がらないと、誰でも焦ってしまうものです。しかし、そんな時こそ冷静に行動することが大切です。最後に、重要なポイントを3つだけ振り返りましょう。
- 慌てず状況確認:まずは停電の範囲を確認し、分電盤から異音や異臭がしないかなど、安全を第一に状況を把握しましょう。
- 原因に応じた正しい手順で復旧:電気の使いすぎであれば家電を減らし、漏電の疑いがあればこの記事で解説した手順で原因回路を特定します。
- 危険を感じたら無理せず専門家へ:少しでも不安を感じたり、危険なサインが見られたりした場合は、迷わずプロの電気工事業者に相談してください。
この記事が、あなたの不安を少しでも解消し、安全な毎日を取り戻す手助けになれば嬉しいです。電気のトラブルは、生活に潜む大切な注意サインです。この機会にご家庭の電気設備を見直してみてください。